住宅購入時に親からの支援を受けるときのポイントと注意点
- お役立ちコラム
親からの支援を受けて住宅を購入することは、経済的な負担を大きく軽減できる魅力的な方法です。
しかし、お金が絡むことで贈与税の問題や家族間のトラブルに発展するケースも見られます。
この記事では、親からの援助を安心して受けるために知っておきたいポイントを3つに絞って、わかりやすく解説していきます。
マイホーム購入を検討している方はもちろん、支援を考えている親御さんにも役立つ内容です。
親からの支援と贈与税の関係

住宅購入時に親から資金の援助を受ける場合、まず最初に確認しておきたいのが贈与税の有無です。
せっかく支援を受けられても、あとから多額の贈与税が発生するようでは、本末転倒ですよね。
ここでは、贈与税がどのようなときに発生するのか、避けるためには何に気をつければいいのかについて解説していきます。
いくらまでもらうと贈与税がかかるのか?
基本的に、親から子へ年間110万円を超える金額を無償で渡した場合、それは「贈与」と見なされます。
そして、この110万円というのは「暦年課税」における基礎控除額と呼ばれるもの。
これを超えた金額に対して、贈与税が課税されます。
例えば、親から300万円を受け取って住宅の頭金にした場合、そのうち190万円が課税対象となります。
この金額に応じて、10%~55%の贈与税が発生する仕組みです。
贈与と見なされないケースとは?
「親からの支援=全て贈与」になるとは限りません。
以下のようなケースでは、贈与税が発生しない、または判断が異なることがあります。
「親が住宅の代金を直接支払ったが、名義を親と子の共有にした貸付として契約書を交わし、返済義務が明確にある」
「法律上、扶養義務がある範囲内の支出とみなされる」ときなどです。
ただし、これらの判断は非常にデリケート。
税務署の見解によっても左右されるため、「これは贈与にならないだろう」と自己判断せず、専門家に事前確認することが大切です。
贈与税が発生した場合の対応と申告方法
もし贈与税の課税対象となる支援を受けた場合は、翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行い、納税する必要があります。
申告を行うには贈与税の申告書、贈与を証明する契約書や振込明細、住宅の売買契約書(住宅取得資金の場合)などさまざまな書類が必要になります。
申告を怠ると、後からペナルティが科されることもあるため、「親からの支援=申告不要」と思い込まず、一度立ち止まって確認することが大切です。
住宅取得等資金の非課税制度とは?

親からの支援によって住宅を購入する際、「贈与税が心配…」という方にとって非常に心強い制度があります。
それが「住宅取得等資金の贈与の非課税制度」です。
この制度を上手に活用すれば、一定額までの贈与が非課税となり、税金の負担を大きく軽減することが可能です。
ここでは、この制度の概要と注意点、手続きについてわかりやすく解説していきます。
制度の概要と対象となる住宅の条件
この非課税制度は、父母や祖父母から住宅の購入資金として贈与を受ける場合に利用できる制度です。通常なら贈与税の対象になる金額であっても、要件を満たす住宅であれば一定額まで非課税で受け取ることができます。
制度を利用するには受贈者(贈与を受ける人)の要件、住宅の要件の要件を満たす必要があります。
受贈者(贈与を受ける人)の要件
多くの要件がありますが、主に以下のような要件を満たしている必要があります。
・贈与者(贈与する人)の直系卑属(子や孫)であること
・贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること
・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
・住宅を取得した年の翌年3月15日までに住み始めること
住宅の要件
非課税制度の対象となる住宅には、例として主に以下のような基準があります。
・床面積が50㎡以上240㎡以下であること
・床面積の2分の1以上が受贈者の居住用であること
特に「将来的に住む予定」や「子どもに貸す予定」の物件では対象外となる場合があるため、慎重な確認が必要です。
非課税枠はいくら?期間や上限に注意
非課税となる金額の上限は、その年の契約日や住宅の性能によって異なります。
例えば、2025年時点(※令和6年1月1日〜令和8年12月31日まで)の目安は省エネ等住宅であれば1000万円の非課税限度額。省エネ等住宅以外の住宅であれば、500万円の非課税限度額となります。
| 住宅の種類 | 省エネ等住宅※ | 左記以外の住宅 |
|---|---|---|
| 非課税限度額 | 1000万円 | 500万円 |
「省エネ等住宅」にはいくつか条件があり、家屋の区分に応じ、省エネルギー性能、耐震性能又はバリアフリー性能のいずれかの基準(省エネ等基準)に適合する住宅用の家屋であることが必要です。
| 家屋の区分 | 省エネ等基準 | ||
|---|---|---|---|
| 省エネルギー性能 | 耐震性能 | バリアフリー性能 | |
| ① 新築をした住宅用の家屋 | 断熱等性能等級 5以上 かつ 一次エネルギー消費量等級 6以上 |
耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) 2以上 又は 免震建築物 |
高齢者等配慮対策等級 (専用部分) 3以上 |
|
② 建築後使用されたことのない 住宅用の家屋 |
断熱等性能等級 5以上 かつ 一次エネルギー消費量等級 6以 |
耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) 2以上 又は 免震建築物 |
高齢者等配慮対策等級 (専用部分) 3以上 |
|
③ 建築後使用されたことのある 住宅用の家屋 |
断熱等性能等級 4以上 又は 一次エネルギー消費量等級 4以上 |
耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) 2以上 又は 免震建築物 |
高齢者等配慮対策等級 (専用部分) 3以上 |
| ④ 増改築等をした住宅用の家屋 | 断熱等性能等級 4以上 又は 一次エネルギー消費量等級 4以上 |
耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) 2以上 又は 免震建築物 |
高齢者等配慮対策等級 (専用部分) 3以上 |
この非課税枠は、先ほど説明した暦年贈与(年間110万円の基礎控除)とは別枠で適用されます。
そのため、条件を満たせば、110万円+非課税枠分の合計額を非課税で受け取れる可能性があります。
ただし、制度には利用期限や改正の可能性があるため、計画的な利用が大切です。
国の税制改正によって非課税枠が縮小されたり、終了したりすることもあるため、制度の最新情報を定期的に確認しましょう。
制度を活用するための手続きと必要書類
この制度を利用するには、必ず贈与税の申告が必要です。「非課税なんだから申告はいらないのでは?」と思われがちですが、申告をしなければ非課税の適用は受けられません。
具体的には、以下のような書類を揃える必要があります。
・贈与税の申告書(非課税の特例適用欄あり)、
・住宅の登記事項証明書
・売買契約書または建築請負契約書のコピー
・住民票(実際に居住することの確認用)
・贈与を証明する書類(振込明細など)
必要書類は、さまざまなケースによって変わってくるので必ず国税庁のホームページでご確認ください。
また、期日を過ぎると、せっかくの非課税枠が使えなくなる可能性があるため、早めの準備が肝心です。
参考:国税庁ホームページ 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
支援に関わる名義と契約の取り扱い

住宅購入において、親から資金の援助を受けた場合、「家の名義をどうするか?」という問題が発生します。
この名義の扱いを間違えると、思わぬトラブルや追加の課税が発生することも。
ここでは、親子間でお金のやり取りがある場合の名義の考え方や、共有にする場合の注意点について解説していきます。
関連記事:二世帯住宅はデメリットだらけ?その理由とメリット&快適に暮らすためのポイント
親子で出資する場合の名義の分け方
例えば、住宅の購入費として親が1,000万円、子が2,000万円を出資したとします。
この場合、「出資割合に応じて名義を分ける」のが原則です。
つまり、親が1/3、子が2/3という共有名義にするのが自然です。
しかし、実際の登記を子の単独名義にしてしまうと、親から子への贈与があったと判断される可能性があります。
贈与税の対象になってしまうリスクがあるため、出資と名義の割合は必ず一致させるようにしましょう。
また、「名義をどうするか」は資産継承の観点からも大切な判断になります。
後々、相続の際に問題が起きないよう、記録や意図を明確にしておくことが重要です。
共有名義にするときの注意点
親子で出資した分だけ共有名義にするのは理にかなっていますが、その一方で共有ならではのデメリットも存在します。
例えば…
・将来的に売却する際は、共有者全員の同意が必要
・相続の際、親の持分が他の兄弟姉妹に分配される可能性がある
・住宅ローン控除が使えない場合もある(共有者がローンを組んでいない場合)
こうした点から、「親の名義は残さず、資金援助分は非課税制度を活用して子の単独名義にする」という方法を選ぶ家庭もあります。
ただし、ケースによって最適な選択肢は異なるため、税理士や不動産専門家に相談したうえで判断することをおすすめします。
親名義で住宅ローンを組むときのリスク
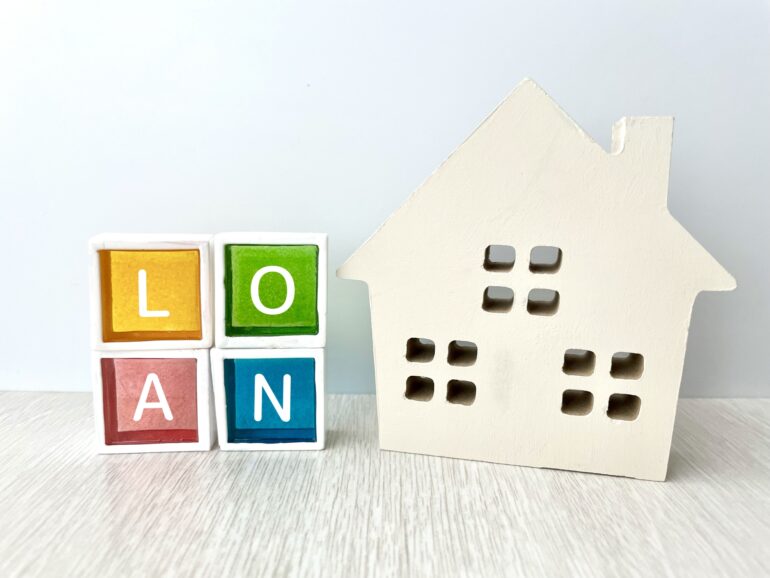
中には「親の信用でローンを組んだほうが有利では?」と考える方もいるかもしれません。
たしかに、年収や信用スコアの高い親のほうが審査が通りやすいケースもあります。
しかし、その場合、住宅の名義も親の単独名義または共有名義になることになります。
例え子が実質的に返済していたとしても、ローン契約者と登記名義人が親であれば、税務上は「親の家」と見なされてしまいます。
さらに、将来的に子へ所有権を移す際には譲渡税や贈与税が発生する可能性もあります。
このように、ローンの名義一つとっても後々大きな問題につながることがあるため、計画段階から慎重な検討が必要です。
関連記事:家を買うのに必要な年収とは?年収200万〜600万円の返済プランや買える家を解説
トラブルを避けるためにしておきたいこと
親からの支援はありがたいものですが、お金が関わることで家族の間に溝ができてしまうケースも少なくありません。
せっかくのマイホーム購入がきっかけで関係がぎくしゃくしてしまっては、本末転倒ですよね。
ここでは、支援を受ける際に意識しておきたい予防策を紹介します。
支援内容は書面で残しておく
「親子なんだから口約束で十分」と思われがちですが、金額が大きいだけに記録を残しておくと、申告の時に手間取らずに済みますし、トラブルを避けることにも繋がります。
特に「贈与」なのか「貸付」なのかを明確にしておかないと、後々相続の場面でトラブルの火種になることがあります。
借入扱いにする場合は、金銭消費貸借契約書を作成し、返済方法も記載しておきましょう。
贈与の場合も、「贈与契約書」として書面に残すことで、税務上の証明にもなります。
事前に家族で話し合いをしておく
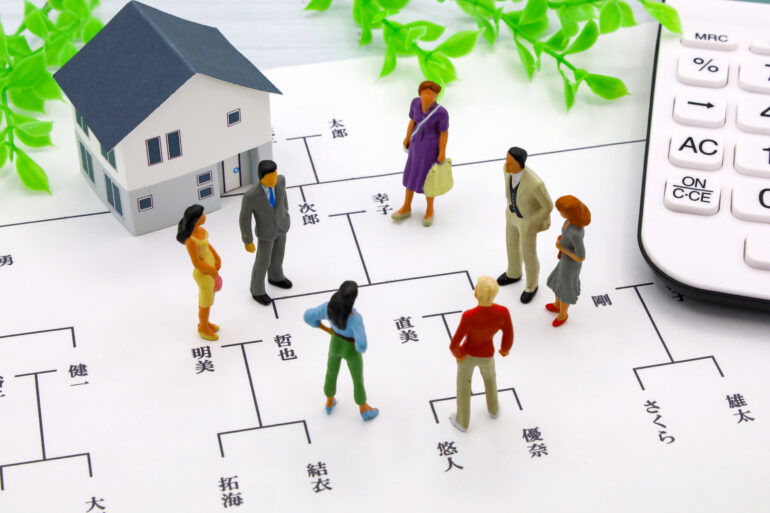
支援を受けるのは子ども世帯であっても、その影響は兄弟姉妹や親族にも及ぶことがあります。
「なぜ自分だけが援助を受けられないのか」と不公平感を招くケースもあるのです。
こうした行き違いを防ぐには、親子間だけでなく兄弟姉妹も含めて事前に説明することが重要です。
話し合いの場を設け、「どういう理由で支援を受けるのか」「将来の相続にどのように影響するのか」を共有しておくと安心です。
専門家(税理士・司法書士)に相談する

贈与税や非課税制度、名義の扱いなどは、素人判断では難しい部分が多いテーマです。
誤った対応をしてしまうと、後から大きな税金を負担することになる可能性も。
そこでおすすめしたいのが、専門家に早めに相談することです。
贈与や非課税制度の適用に関するアドバイスなら税理士に、登記や契約書の作成についての具体的な相談は司法書士が専門です。
初期段階での相談が、後々の安心につながります。
安心して援助を受けるために心がけること
親からの支援を受けて住宅を購入することは、経済的な負担を大きく減らせる大きなメリットがあります。
しかしその一方で、贈与税の問題や名義の扱い、家族間の公平性など、注意しなければならない点も数多く存在します。
今回ご紹介したように、
・贈与税の基礎知識を理解しておくこと
・住宅取得等資金の非課税制度を活用すること
・名義や契約を明確に整理し、書面に残すこと
この3つを意識するだけでも、後々のトラブルを避ける大きな助けになります。
住宅購入は人生の大きな節目。
だからこそ、家族全員が納得できる形で支援を受け、安心して新しい生活を始められるようにしたいですね。
アイウッドは地元熊本で創業して半世紀。
約8,000棟の豊富な実績でお客様のお悩みに寄り添った提案を行っています。
夢のマイホームに向けて、少しでも気になることがあれば経験豊富なアイウッドにご相談ください。


