家づくりは何から始める? 初心者向け完全ガイド|流れ・期間・費用を徹底解説
- お役立ちコラム
家づくりを考え始めたものの、「何から手をつければいいのか分からない……」「失敗したらどうしよう……」と不安を感じていませんか?
人生で最も大きな買い物だからこそ、慎重に進めたいですよね。実は、家づくりで後悔する人の多くは「正しい順序」を知らずに進めてしまったことが原因かもしれません。
そこでこの記事では、家づくり初心者の方に向けて以下の内容を解説します。
・家づくりを始める最初の3ステップ
・検討開始から入居までの全体スケジュール
・予算や費用の考え方(熊本エリアの相場付き)
・よくある後悔ポイントと失敗しない対策
熊本を中心に8,000棟以上の施工実績を持つアイ-ウッドが、これまでの経験をもとに「後悔しない家づくり」のポイントをお伝えします。
最後まで読めば、家づくりの全体像が明確になり、安心して第一歩を踏み出せるはずです。
家づくりは何から始める?【最初の3ステップ】

家づくりは、理想の暮らしをイメージすることから始まります。
ただ、「何を基準に考えればいいか分からない」という方も多いでしょう。そんな時は以下の3つのステップを意識して考えてみることをおすすめします。
①家族で理想の暮らしを話し合う
家づくりで最も大切なのは、「どんな暮らしがしたいか」を家族全員で共有することです。
デザインや間取りを考える前に、まずは理想のライフスタイルを具体的にイメージしてみましょう。
ライフスタイルのイメージ例
- 家族の時間を大切にしたい:リビングを広くして家族が自然と集まる空間に
- 仕事や趣味に集中したい:書斎やワークスペースを確保
- 家事を効率化したい:回遊動線や家事ラク設備を重視
- 子どもの成長に合わせたい:可変性のある間取りを検討
- 老後も安心して暮らしたい:バリアフリー設計やワンフロア完結の間取り
- ペットと快適に暮らしたい:ペット専用スペースや傷に強い素材
このとき、InstagramやPinterestで気に入った住宅の写真を保存しておくと、建築会社との打ち合わせで「こんな雰囲気が好き」と伝えやすくなります。
アイ-ウッドでは、デザイン性・機能性・快適性を備え、テーマごとに規格されたラインナップから選べるコンセプト住宅をご提案。
さらにそこから一つ一つ、お客様のライフスタイルに合わせ、間取りや設備、インテリアなどにこだわった自由設計の注文住宅づくりを進めていきます。
漠然としたイメージでも問題ありません。プロが言語化をお手伝いします。
アイ-ウッドのコンセプト住宅はこちら
②予算の目安を把握する
理想の暮らしをイメージしたら、次は現実的な予算を把握しましょう。
家づくりにかかる費用は大きく分けて3つあります。土地の取得費、建築費、諸費用の3つです。
|
地域 |
建築費(万円) |
土地取得費(万円) |
諸費用(万円)※ |
|
全国 |
3,512.0 |
1,495.1 |
500.71 |
|
三大都市圏 |
3,479.5 |
1,941.5 |
542.1 |
|
首都圏 |
3,505.6 |
2,285.0 |
579.06 |
|
近畿圏 |
3,366.7 |
1,826.0 |
519.27 |
|
東海圏 |
3,615.7 |
1,359.8 |
497.55 |
|
その他地域 |
3,549.1 |
985.0 |
453.41 |
|
熊本県 |
3,468.5 |
903.6 |
437.21 |
※建築費、土地取得費は住宅金融支援機構「フラット35利用者調査 2024年度集計表」を参考に表を作成
※諸費用は建築費と土地取得費の合計の10%で計算
上記表を参考にすると、熊本で土地付きの注文住宅を建てる場合、4,809.31万円(建築費+土地取得費+諸費用)が予算の目安といえます。ただし、実際はエリアや建物のグレードによって大きく変動しますので、具体的な資金計画は建築会社と一緒に進めていきましょう。
年収別の予算目安
一般的に無理のない住宅ローンの借入額の目安は「年収の5〜6倍」といわれています。また、返済比率(年収に占める年間返済額の割合)は25〜35%以内に抑えることが理想とされています。
- 年収400万円:総額2,000〜2,400万円
- 年収500万円:総額2,500〜3,000万円
- 年収600万円:総額3,000〜3,600万円
- 年収700万円:総額3,500〜4,200万円
※実際の借入可能額は、金利や返済期間、他のローン状況により変動します。無理のない返済計画を立てるために、早めに資金相談を行うのがおすすめです。
③情報収集の方法を知る
予算の目安がついたら、本格的に情報収集を開始しましょう。
効果的な情報収集の方法
1. Web・SNSで基礎知識を学ぶ
- 家づくりの流れや基礎知識を理解する
- Instagram・Pinterestで好みのテイストを探す
- 住宅会社の公式サイトで施工事例をチェックする
メリット:自分のペースで進められる
デメリット:情報が多すぎて迷いやすい
2. 資料請求でカタログを取り寄せる
- 気になる住宅会社のカタログを一括請求する
- 各社の強みや価格帯を比較する
- 施工事例や標準仕様を確認する
メリット:複数社を効率的に比較できる
デメリット:紙面情報だけでは実物のイメージがつきにくい
3. 住宅展示場・完成見学会に参加する
- 実際の建物の質感や空間を体感する
- 営業担当者と直接話して相性を確認する
- 住宅性能(断熱・気密など)を肌で感じる
メリット:リアルな暮らしのイメージが湧く
デメリット:時間と労力がかかる
情報収集の進め方は、「Webで基礎学習 → 資料請求で絞り込み → 展示場で最終確認」の流れがおすすめです。この順序で進めると、効率的に理想の建築会社を見つけることができます。
家づくりにかかる期間は?【全体スケジュール】

家づくりは、検討開始から入居まで9〜15カ月程度かかるといわれています。
ローコスト住宅など仕様がある程度決まっている場合は、着工から完成まで最短2〜3カ月で完成するケースもあります。
ただし、土地探しの状況や打ち合わせの内容によって大きく変動するため、余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。
全体スケジュールの目安
|
ステップ |
期間 |
|
情報収集〜予算決め |
約1〜2カ月 |
|
建築会社・土地の選定 |
約1〜2カ月 |
|
ローン手続き〜打ち合わせ |
約3〜4カ月 |
|
工事 |
約3〜6カ月 |
|
引き渡し・入居 |
約1カ月 |
時期別のポイント
- 春入居を希望する場合:前年の夏頃から動き始める
- 子どもの入学に合わせたい場合:1年以上前から計画する
- 消費税増税前などの場合:さらに余裕を持って2年前から検討する
注意点
人気エリアの土地はすぐに売れてしまうため、土地探しには時間がかかることがあります。条件を見直す柔軟さを持ちながら、余裕あるスケジュールで進めましょう。
家づくりの基本的な流れ【12ステップ】

ここからは、家づくりの具体的な流れを12のステップに分けて解説します。全体の流れを把握しておくことで、今自分がどの段階にいるのかを理解しながら進めることができます。
ステップ1:情報収集
家づくりの第一歩は、情報を幅広く集めることです。
Web・雑誌・SNSで基礎知識を学び、住宅展示場やモデルハウスを見学して実際の空間を体感しましょう。
また、複数の建築会社から資料を取り寄せ、少なくとも3〜5社を比較検討するのがおすすめです。
ポイント
- デザインの方向性(モダン・ナチュラル・和モダンなど)
- 住宅性能(断熱性・気密性・耐震性など)
- 価格帯と標準仕様の内容
- 保証・アフターサポート
- 営業担当者との相性・対応力
モデルハウスは実際の標準仕様よりも高性能・高仕様で建てられている場合もあります。
見学時は、間取りの動線・収納の配置・窓の位置や大きさなどを意識しながら、自分たちの生活に合うかをチェックしましょう。
SNSや口コミも参考になりますが、情報の発信元を確認し、信頼性の高い住宅会社・公的機関の情報を活用することが大切です。
ステップ2:予算決め
理想の住まいを思い描いたら、次は現実的な予算を決めるステップです。家づくりにかかる費用は、「建築費」「土地代」「諸費用」の3つに大きく分けられます。
まずは自己資金(頭金)を確認し、住宅ローンの借入可能額を試算した上で、無理のない総予算を立てましょう。
やること
・自己資金(頭金・予備資金)を確認する
・住宅ローンの借入可能額と返済シミュレーションを行う
・総予算(建物+土地+諸費用)を決定する
ポイント
「借りられる額」と「返せる額」は、必ずしも同じではありません。長く安心して暮らすためには、無理のない返済計画を立てることが最も大切です。
資金計画でチェックしておきたいこと
・月々の返済額は収入の25〜35%以内か
・教育費・老後資金など、将来の支出も考慮できているか
・頭金は物件価格の10〜20%程度を目安にできているか
・登記・税金・火災保険・引っ越し費用などの諸費用(総額の7〜10%程度)を別途確保できているか
・ボーナス返済に過度に頼らず、固定給だけで返済できる計画になっているか
住宅ローンの主な種類
変動金利:金利が低く設定されているが、将来的に上昇するリスクがある
全期間固定金利(例:フラット35):金利はやや高めだが、返済額が固定されるため安心感がある
固定期間選択型:一定期間だけ金利が固定され、その後は変動または再固定を選択できる
金利タイプや返済期間の違いによって、総返済額が数百万円単位で変わることもあります。将来のライフプランや家計の変化も見据えて、慎重に比較・検討しましょう。
早めに住宅ローンの事前審査(仮審査)を行い、現実的な借入可能額を把握しておくと、土地探しやプランづくりがスムーズになります。
ステップ3:建築会社の選定
理想の家づくりを実現するには、信頼できる建築会社選びが重要なステップです。
ここでは、比較検討から最終決定までの流れを整理しておきましょう。
やること
- 気になる建築会社を3〜5社にリストアップする
- 各社のモデルハウスや完成見学会に参加し、実際の建物を確認する
- 概算見積もりを取得して比較する
- 条件・相性を踏まえて、最終的に1社を選定する
建築会社選びの比較ポイント
|
項目 |
チェック内容 |
|
施工品質 |
施工事例の確認、構造見学会への参加(可能なら) |
|
住宅性能 |
断熱等級・気密性能(C値)・耐震等級などの数値を比較 |
|
デザイン力 |
好みのテイストやライフスタイルを実現できるか |
|
価格 |
坪単価と標準仕様の範囲を確認(地域・仕様で差あり) |
|
提案力 |
ヒアリング力やプランの提案内容の質 |
|
アフターサポート |
保証期間、定期点検の内容、修繕対応の有無 |
|
営業担当者 |
相性やレスポンスの速さ、信頼感 |
注意点
「坪単価が安い」というだけで選ぶのは危険です。標準仕様の範囲が狭く、オプション費用がかさむケースもあります。必ず「総額」で比較し、何が標準で何がオプションなのかを明確にしておきましょう。
また、建築会社との相性も重要です。家づくりは平均して1年近くかかるプロジェクトなので、信頼できる担当者と進めることが満足度の高い家づくりにつながります。
ステップ4:土地の選定

理想の家を建てるには、土地選びがとても重要です。
建てたいエリアや条件を整理し、建築会社と相談しながら現実的な候補を探していきましょう。
やること
- 希望エリア・条件(広さ、予算、環境)を整理する
- 不動産会社や建築会社に土地探しを依頼する
- 気になる土地の現地確認をする
- 用途地域・建ぺい率・容積率などの法規制をチェックする
土地選びのポイント
- 立地条件:通勤・通学、買い物、病院へのアクセス
- 周辺環境:日当たり・騒音・隣地との距離・街並み
- 法規制:建築可能な建物の大きさや高さ
- インフラ:上下水道・ガスの整備状況、道路との接道条件
- 地盤:改良工事が必要かどうか(追加費用の有無)
- ハザードマップ:浸水リスク・土砂災害警戒区域など自治体の最新情報を確認
良い土地を見つけるコツ
- 平日と休日、昼と夜で現地を訪れ、交通量や雰囲気の変化を確認する
- 建築会社の担当者に同行してもらい、地盤や法規制を専門家の目で確認する
- 「完璧な土地はない」と心得て、条件の優先順位と妥協点を明確にする
土地探しは、建築会社の選定と並行して進めるのがおすすめです。なぜなら、土地の形状や法規制によって建てられる家の大きさや間取りが変わるからです。建築会社と一緒に進めれば、「買ってから建てられない」というトラブルを防ぐことができます。
ステップ5:建築プランの設計・見積もり
建築会社が決まったら、いよいよ理想の間取りプランづくりへ。
家族の暮らし方や将来のライフステージを踏まえて、納得のいくプランを一緒に作り上げましょう。
やること
- 建築会社に間取りプランを提案してもらう
- 複数プランを比較検討し、生活動線や収納などを見直す
- 概算見積もりを確認し、必要に応じて修正・調整を繰り返す
間取りプランで確認すべきこと
- 生活動線:家事や通勤準備がスムーズに行えるか
- 日当たり・風通し:リビングや寝室が快適な方位・採光になっているか
- 収納量:家族の荷物を十分に収められるか
- 将来の変化:子どもの成長や親との同居にも対応できるか
- プライバシー:道路や隣家からの視線を適度に遮れるか
間取り検討のコツ
まずは、今の住まいで不便に感じていることをリスト化してみましょう。その不満を解消することが、満足度の高い家づくりにつながります。
間取りの例
・洗濯物を干すたびに階段を上り下りして大変 → 1階に洗濯動線を集約
・玄関が狭く靴があふれる → シューズクローゼットを広めに確保
・冬にリビングが寒い → 断熱性能を高めたプランを検討
見積もりで注意すべき点
- 坪単価だけでなく「総額」で判断する
- 標準仕様とオプションの境界を明確にする
- 外構工事・地盤改良費が含まれているか確認する
- 諸費用(登記・税金など)も忘れずに
- 見積もりは同条件で複数パターンを出してもらい、比較する
見積もり段階では、妥協せずに納得できるまで相談することが大切です。プラン内容・住宅性能・費用の全てを把握した上で、「予算内で最も理想に近い家」を形にしていきましょう。
ステップ6:土地の購入申し込み
希望条件に合う土地が見つかったら、いよいよ購入申し込みの段階です。
このステップでは、契約に進む前の確認と、重要な法的手続きを丁寧に進めましょう。
やること
- 希望の土地が見つかったら購入申し込みをする
- 手付金(代金の5〜10%)を準備する
- 宅地建物取引士による重要事項説明を受ける
- 内容を確認の上、売買契約を締結する
注意点
買主都合のキャンセルでは、原則として手付金は戻ってきません。やむを得ない事情がある場合でも手付金は放棄する必要があるので、注意が必要です。契約前に必ず以下を確認しましょう。
- 建築会社に土地の法的制約や地盤状況を事前チェックしてもらう
- 周辺環境・日照・交通アクセスなどを再度現地確認する
- 契約内容・支払条件を十分に理解する
重要事項説明でチェックすべきポイント
- 土地の権利関係(所有権・抵当権などの有無)
- 法令上の制限(用途地域、建ぺい率、容積率、高さ制限など)
- インフラ整備状況(上下水道・ガス・電気・道路の接道条件)
- 周辺環境・災害リスク(浸水・土砂災害警戒区域、騒音、臭気など)
重要事項説明は専門用語が多く、初めての方には分かりづらい内容です。しかし、この段階での確認不足が後々のトラブルにつながることもあります。分からない点はその場で質問し、納得した上で契約を結びましょう。
ステップ7:住宅ローンの審査

住宅ローンは 「事前審査 → 本審査 → 金銭消費貸借契約(金消契約)」 の順で進みます。
複数行を比較し、金利だけでなく総コストと付帯条件まで確認しましょう。
やること
- 金融機関を選定する(都市銀行、地方銀行、ネット銀行など)
- 住宅ローンの事前審査を申し込む
- 事前審査通過後、本審査を申し込む
- 審査承認後、金消契約を締結する
事前審査で求められる主な書類
- 本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
- 収入証明書類(源泉徴収票、確定申告書など)
- 物件資料(土地・建物の概要)
本審査で追加確認されやすい項目
- 団体信用生命保険(団信)の加入可否(健康状態の告知)
- 転職・雇用形態の変更の有無(勤続・収入の安定性)
- 他の借入状況の変化(自動車・カードローン・リボ など)
住宅ローン選びのポイント
複数の金融機関に同時申し込みをして条件を比較することができます。金利だけでなく、以下の項目も確認しましょう。
- 金利タイプ(変動、固定、固定期間選択型)
- 諸費用(事務手数料、保証料)
- 団体信用生命保険の内容
- 繰り上げ返済の手数料
- 借入後のサポート体制
注意点
- 事前審査に通っても本審査で落ちるケースがある
- 審査期間中は他のローン(車など)を組まない
- 転職や収入の変化があると審査に影響する
住宅ローンは30年以上の長期返済になることが多いため、将来のライフプランも考慮して慎重に選びましょう。
ステップ8:土地・建物の契約
土地が決まり、住宅ローンの審査も進んだら、次はいよいよ契約手続きのステップです。
建築会社とは「工事請負契約」、土地の売主とは「売買契約」を結び、家づくりを正式にスタートさせます。
やること
- 建築会社と工事請負契約を締結する
- 契約金(工事代金の10%程度)を支払う
- 最終プラン・仕様を確定する
- 土地の売買契約を完了させる(未契約の場合)
契約時に確認すべきこと
- 契約書の内容(工期、支払条件、キャンセル規定 など)
- 図面と仕様書の整合性(プラン・設備・仕様が契約書と一致しているか)
- 追加工事の取り決め(変更が発生した場合の手続き・費用負担のルール)
- 保証内容(瑕疵担保、地盤保証など)
- 引き渡し時期(完成・引き渡し予定日、遅延時の対応方法)
工事請負契約書の主な内容
- 工事内容:建物の仕様・設備・間取りなどの詳細
- 工事代金:総額と支払いスケジュール(着工時・中間・完工時など)
- 工期:着工日と完成予定日、天候や追加工事による変更
- 追加変更:変更時の承認手続きと費用負担方法
- 契約解除:キャンセル時の条件・違約金・返金規定
注意点
契約書は法的な効力を持つ重要な書類です。分からない点や疑問点があれば、契約前に必ず質問して解消しておきましょう。
また、契約後の大幅なプラン変更は、工期の遅延や費用増加につながる可能性があるため、契約前に納得できるまで設計・仕様を詰めておくことが大切です。
保証内容の確認
- 瑕疵担保責任保険:構造部分や雨水の浸入を10年間保証(法律で義務化)
- 地盤保証:地盤沈下による建物の損害を保証
- 住宅設備保証:キッチンやバスなどの設備の保証期間
ステップ9:間取り・設備など詳細打ち合わせ

基本プランと契約内容が固まったら、次は家の細部を決める打ち合わせです。
この段階では、暮らしの快適さや使い勝手を左右する「配置・素材・設備」を一つずつ確定していきます。
やること
- コンセントやスイッチ、照明など電気設備の位置決め
- 壁紙・床材・建具など内装仕様の決定
- キッチン・バス・トイレなど住宅設備の詳細選定
- 駐車場や植栽など外構(エクステリア)計画
詳細打ち合わせで決めること
|
カテゴリ |
主な確認項目 |
|
電気設備 |
コンセントの位置と数(家電配置を考慮)/スイッチの位置(動線に合わせて)/照明の種類・明るさ/テレビ・インターネット配線計画 |
|
内装仕様 |
壁紙・天井クロスの色・質感/床材(フローリング・タイルなど)/建具(ドア・引き戸)のデザインと色調/造作家具(カウンター・収納棚など |
|
住宅設備 |
キッチン(グレード・色・収納レイアウト)/バス・トイレ(サイズ・機能・デザイン)/洗面台(収納力・ミラー形状)/給湯器(ガス・電気・エコキュートなど) |
|
外構(エクステリア) |
駐車場(台数・素材)/アプローチ・門扉の配置/植栽や庭のデザイン/フェンス・目隠しの高さと素材 |
打ち合わせのコツ
- 実物サンプルを必ず確認する:カタログや画像と実物では質感・色味が異なるため、必ず現物を確認
- 生活をシミュレーションする:朝の準備・洗濯・掃除など実際の生活シーンを想像して決定する
- 優先順位をつける:迷った場合は「毎日使う場所」「生活に直結する箇所」から決める
- 家族全員で意見を出し合う:後で「聞いていない」とならないよう、共有しながら進める
注意点
この段階での変更は可能ですが、着工が近づくほど変更が難しくなります。特にコンセント位置や配線関係は、着工後に変更できないことが多いため慎重に決めましょう。
また、オプション追加で予算オーバーにならないよう、常に総額を意識しながら決めていきましょう。外構・照明・カーテンなどは「別契約」になるケースもあるため、見積もりの範囲を確認しましょう。
アイ-ウッドのサポート
アイ-ウッドでは、ショールームで実際の設備や素材を見ながら打ち合わせが可能です。経験豊富なスタッフが、デザイン・機能・コストのバランスを考え、お客様のライフスタイルに合った最適なプランをご提案します。
アイ-ウッドの展示場はこちら
ステップ10:発注契約の締結
詳細打ち合わせが全て終わったら、いよいよ発注契約(最終契約)です。
この段階では、これまでの内容を書面で確定し、正式に工事をスタートできる状態にします。
やること
- 詳細打ち合わせの内容を最終確認する
- 最終見積もりを確認する
- 発注契約(正式な工事契約)を締結する
- 着工に向けた準備(地鎮祭・近隣あいさつなど)を進める
最終確認のポイント
|
確認項目 |
内容 |
|
間取り図面 |
希望通りのレイアウト・サイズ・方位になっているか |
|
設備仕様 |
打ち合わせ内容(キッチン・照明・内装材)と一致しているか |
|
総額の変更 |
オプション追加・仕様変更による金額増減を反映しているか |
|
工期スケジュール |
着工日・上棟日・完成予定日が現実的か |
|
支払いスケジュール |
中間金・最終金の支払い時期・金額が明記されているか |
発注契約書の主な内容
- 最終的な工事内容の確定(仕様・設備・間取りの詳細)
- 工事代金の総額と支払い方法(着工金・中間金・完工金)
- 工期(着工日・完成予定日・遅延時の扱い)
- 追加変更工事の手続き(費用発生・承認方法)
- 保証・アフターサポート(瑕疵保険・メンテナンス体制 など)
注意点
発注契約後の変更は、追加費用や工期延長の原因になることがあります。不明点や不安があれば、必ずこの段階で解消しておきましょう。
また、契約書・図面・仕様書の内容に差異がないかを細かくチェックすることが大切です。後のトラブル防止には、口頭ではなく書面での確認が欠かせません。
着工前の準備
|
項目 |
内容 |
|
地鎮祭の実施 |
希望する場合は日程と費用を早めに相談 |
|
近隣へのあいさつ |
工事の騒音・車両出入りに配慮し、あいさつ回りを事前に実施 |
|
連絡体制の確認 |
工事中の連絡窓口(現場監督・担当営業)を明確にする |
いよいよ着工間近です。ここまでの確認を丁寧に行っておくことで、工事期間中も安心して家づくりを見守ることができます。
ステップ11:着工

契約が完了したら、いよいよ工事が始まります。
基礎から上棟、内装、最終検査までの一連の工程を理解しておくことで、安心して家づくりを見守ることができます。
やること
- 地鎮祭(希望する場合)
- 着工・基礎工事
- 上棟式(希望する場合)
- 構造・内装工事
- 完了検査(建築基準法の適合確認)
工事の主な流れ
- 地鎮祭
土地の神様に工事の安全を祈願する儀式です。最近では省略する方も多いですが、家族の節目として行うケースもあります。地縄張り(建物位置の確認)後に実施されるのが一般的です。
- 着工・基礎工事
建物を支える基礎をつくります。配筋検査(住宅瑕疵担保責任保険に基づく第三者検査)で、鉄筋の太さ・配置が設計どおりかを確認し、合格後にコンクリートを打設します。
- 上棟式
柱・梁などの構造体を組み上げ、屋根の骨組みまで完成させます。この日に「上棟式」を行う場合もあり、施工関係者への感謝と無事を祈る伝統行事です。
- 構造・内装工事
外壁や屋根の施工、断熱材の充填、配線・配管、内装仕上げなどが進みます。この段階で家の形がはっきりと見えてきます。現場確認の際は、収納位置・スイッチ配置など最終チェックを行うのもおすすめです。
- 完了検査
建築基準法に基づく公的検査で、建物が設計図書どおりに建てられたかを確認します。検査に合格すると「検査済証」が発行され、住宅ローンの最終実行や登記の手続きに必要になります。
注意点
工事中の変更は基本的に難しく、追加費用も高額になる可能性があります。どうしても変更が必要な場合は、早めに建築会社へ相談しましょう。
また、天候や資材調達の影響で、予定より工期が延びることもあります。多少の遅れを想定しておくことで、余裕を持って進行を見守れます。
ステップ12:引き渡し・入居

全ての工事が完了したら、いよいよ待ちに待った新居への入居です。
引き渡し前後には確認すべき書類や手続きが多いため、一つずつ丁寧に進めましょう。
やること
- 完成立会い(施主検査)で傷や不具合をチェック
- 鍵の引き渡しを受ける
- 住宅ローンの融資実行
- 引っ越し・入居を実施
引き渡し時の確認ポイント
|
チェック項目 |
内容 |
|
傷・汚れ・設備の動作確認 |
壁・床・建具・住宅設備の表面や作動を確認 |
|
図面通りの施工 |
間取り・窓位置・造作寸法が契約図面通りになっているか確認 |
|
ドア・窓の開閉 |
スムーズに動くか、鍵が正常に作動するか |
|
水回りの動作確認 |
蛇口・排水の水漏れや異音の有無を確認 |
|
照明・コンセントの動作 |
全室の電源・スイッチ・換気扇などをチェック |
※完成立会いでは、建築会社の担当者立会いのもと記録を残すことが重要です。後日修繕が必要な箇所は、書面または写真で記録しておきましょう。
受け取る書類
|
書類名 |
内容 |
|
保証書 |
構造・防水・住宅設備などの保証内容(瑕疵担保責任保険を含む) |
|
取扱説明書 |
設備機器(給湯器・キッチン・浴室など)の使用方法 |
|
完了検査済証 |
建築基準法に基づく検査合格証。登記・融資に必須 |
|
鍵一式 |
メインキー・マスターキー・玄関電子キーなど |
|
アフターサポート案内 |
定期点検・メンテナンススケジュール・連絡先 |
特に「完了検査済証」と「保証書類」は、住宅ローン控除や登記・保険申請に必要となるため大切に保管しましょう。
引き渡し後の流れ
- 住宅ローン融資実行:金融機関から建築会社へ工事代金の最終金が支払われます
- 所有権登記:司法書士が建物の登記手続きを行います
- 引っ越し:新居への引っ越しを進めます
- 各種手続き:住所変更、公共料金の契約などを行います
入居後のチェック
新居に住み始めてから気づく小さな不具合もあります。気になる点は早めに建築会社へ連絡し、アフターサポートを活用しましょう。
- 建具(ドア・窓)の調整が必要な箇所はないか
- 設備の使い方で不明点やエラー表示はないか
- 結露・通気性に問題はないか
- 壁紙の浮きや床のきしみなど、初期不具合がないか
住宅メーカーによっては、3カ月・6カ月・1年点検などの定期訪問を実施しています。入居後も継続的にメンテナンスを受けることで、長く快適な住まいを保てます。
家づくりでよくある後悔ランキング

家づくりでは「建ててから気づく失敗」が少なくありません。ここでは、多くの人が実際に後悔したポイントをランキング形式で紹介します。あらかじめ知っておくことで、同じ失敗を防ぐことができます。
【1位】間取りや生活動線が悪く、ストレスを感じる
よくある後悔の声
- 「キッチンから洗濯機まで遠くて、家事が大変」
- 「トイレが1階だけで、夜中に階段を降りるのが面倒」
- 「玄関からリビングまでの動線が悪く、来客時に気を使う」
- 「収納が各部屋に分散していて、物の出し入れが不便」
間取りの失敗で最も多いのが、生活動線のシミュレーション不足です。図面上では便利そうに見えても、実際に生活してみると「動線が遠い」「家事に時間がかかる」と感じるケースが多く見られます。
対策:生活動線を徹底的にシミュレーションする
間取りを考えるときは、見た目だけでなく「暮らしの流れ」を想像することが重要です。
朝の準備動線:寝室→洗面所→クローゼット→キッチン→玄関までスムーズか
家事動線:キッチン→洗濯機→物干し場→収納の距離が短く効率的か
来客動線:玄関からリビングへ入る経路がプライベート空間を通らないか
夜間動線:寝室からトイレまでの距離と照明配置は安全か
【2位】冷暖房の効きが悪く、室内環境が快適でない
よくある後悔の声
- 「夏は2階が暑すぎて、エアコンをつけても涼しくならない」
- 「冬は足元が冷えて、暖房費が高い」
- 「部屋ごとの温度差が激しく、廊下やトイレが寒い」
- 「結露がひどく、カビが発生してしまった」
原因の多くは、断熱性能・気密性能の不足にあります。デザインを優先して性能面を軽視すると、住み心地だけでなく光熱費・健康にも悪影響を及ぼします。特に冬場の急激な温度差によるヒートショックは、家庭内事故の主な原因となっています。
対策:住宅性能を重視する
快適で健康な住まいをつくるためには、以下の性能を確認しておきましょう。
断熱性能(UA値):数値が小さいほど断熱性能が高い。熊本など温暖地ではUA値0.6以下が目安
気密性能(C値):数値が小さいほど隙間が少なく、空調効率が良い。1.0以下が理想
窓の性能:樹脂サッシ+Low-E複層ガラスで熱損失を抑制
換気システム:第1種または第3種換気で空気の流れを計画的に保つ
この他、「BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)」の星数で性能を確認するのもおすすめです。
【3位】収納スペースが足りず、物があふれている
よくある後悔の声
- 「収納が少なくて、部屋に物が出しっぱなしになっている」
- 「季節ごとの衣類や布団を収納する場所がない」
- 「子どもの成長とともに物が増えて、収納が足りなくなった」
- 「収納はあるけど、奥行きが深すぎて使いにくい」
収納の失敗は、量だけでなく配置と使いやすさの設計不足が原因です。建築時には物量が少なく見えても、生活が始まると想定以上に荷物が増えるのが一般的です。
対策:収納計画をしっかり立てる
収納は「面積」だけでなく「配置」と「使いやすさ」を考慮して計画しましょう。
現在の荷物量を把握する:引っ越し前に荷物リストを作成し、量と種類を把握する
将来の変化を想定する:子どもの成長・趣味・季節用品などの増加を見込む
使う場所に収納を配置する:「使う場所」と「しまう場所」を近くに設け、動線を短縮
適切な奥行きを選ぶ:用途に応じて45cm・60cm・90cmなど適切な奥行きを選ぶ
収納の種類と使い分け
- ウォークインクローゼット:衣類をまとめて収納、着替えもできる
- パントリー:食品や日用品のストックに便利。キッチン近くが理想
- シューズクローゼット:靴や外遊び用品、ベビーカーなどを収納可能
- 小屋裏収納:使用頻度の低い季節用品・思い出の品をまとめて収納
収納率(収納面積 ÷ 延床面積)は、全体の10〜15%程度を目安に計画すると、使いやすい住まいになります。
家づくりで後悔しないためのポイント

ここまで、家づくりで多くの人が後悔する理由を紹介してきました。では、どうすればそのような失敗を防げるのでしょうか?ここでは、後悔しない家づくりを実現するための4つのポイントを解説します。
①間取りは生活をシミュレーションする
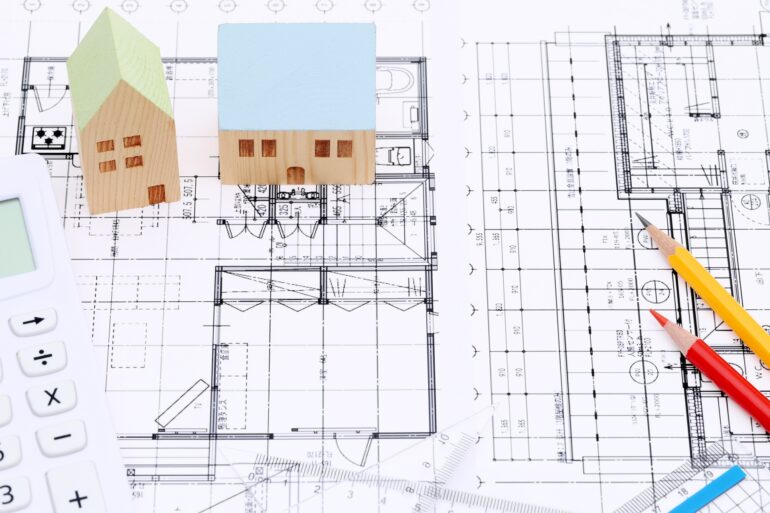
間取りを決める際は、図面を眺めるだけでなく、実際の生活シーンを具体的にイメージすることが大切です。
図面上の線や数字だけでは見えない動線の不便さや暮らしの流れを、体感的に確認しましょう。
シミュレーションのポイント
朝の準備を想像する
- 寝室→洗面所→クローゼット→キッチン→玄関の流れがスムーズか
- 家族が同時に準備しても洗面所やトイレが混雑しないか
家事の流れを考える
- 洗濯(洗う→干す→取り込む→たたむ→しまう)の動線が短いか
- キッチン→ダイニング→収納までの移動がスムーズか
- 掃除や片付けをする際に動線が交差していないか
来客時を想定する
- 玄関からリビング・客間までの動線にプライベート空間が見えないか
- トイレの位置が来客にも使いやすく、視線が気にならないか
将来の変化を考える
- 子どもの成長後、部屋の使い方を変えられるか
- 親との同居や老後を見据え、階段の負担やバリアフリー対応が可能か
チェックリストを活用する
間取り図を見ながら、以下の項目をチェックしましょう。
□ 各部屋の広さは十分か
□ 収納は使う場所に適切に配置されているか
□ 日当たり・風通しは良好か
□ 家具配置を具体的にイメージできるか
□ コンセント・照明の位置は適切か
□ 音やにおいの伝わり方に問題はないか
②住宅性能を重視する

見た目やデザインも大切ですが、快適さ・安全性・省エネ性を支えるのは住宅性能です。特に「断熱性」「気密性」「耐震性」は、長く安心して住むための基本性能となります。
重視すべき住宅性能
- 断熱性能(UA値)
UA値(外皮平均熱貫流率)は、住宅の断熱性能を表す数値です。小さいほど熱が逃げにくく、高断熱といえます。
- 断熱等級5(ZEH相当):UA値0.6以下(熊本エリア)
- 断熱等級6(HEAT20 G2相当):UA値0.46以下(熊本エリア)
- 断熱等級7(HEAT20 G3相当):UA値0.26以下(熊本エリア)
断熱性能を高めることで、冷暖房費の削減・温度差の少ない快適な室内環境・ヒートショックの予防が期待できます。
- 気密性能(C値)
C値(相当隙間面積)は、建物の隙間の少なさを示す数値で、小さいほど高気密です。
- 高気密住宅の目安:C値1.0以下
- 超高気密住宅:C値0.5以下
高気密な家は、冷暖房の効率が良く、計画換気によってカビや結露の発生を抑制できます。
- 耐震性能(耐震等級)
耐震等級は、地震に対する建物の強さを表す指標です。
- 耐震等級1:建築基準法の最低基準(震度6強〜7の地震で倒壊しない)
- 耐震等級2:等級1の1.25倍の強度(学校や病院レベル)
- 耐震等級3:等級1の1.5倍の強度(消防署や警察署レベル)
熊本地震の経験から、耐震等級3の重要性がより認識されるようになりました。
見るべき数値とポイント
建築会社を選ぶ際は、以下の情報を必ず確認しましょう。
UA値とC値の実測値:カタログ値だけでなく、実際の施工での数値を確認
耐震等級:できれば耐震等級3を標準仕様としているか
窓の性能:樹脂サッシ、複層ガラス(Low-Eガラス)を使用しているか
換気システム:第1種換気(熱交換型)など、計画的な換気ができるか
アイ-ウッドの住宅性能
- BELS全棟標準表示:基準レベル以上の優れた省エネ性能のみが認定される
- 断熱性能:熊本の強化外皮基準(UA値0.6以下)をクリア
- 耐震等級3:最高等級の構造設計で地震にも強い
快適性と安全性を両立した、長く住み継げる住まいを提供しています。詳しくはこちらをご覧ください。
③収納計画をしっかり立てる

収納は「とりあえず作っておけばいい」というものではありません。使いやすく、片付けやすい収納を実現するには、量・配置・用途を明確にしておきましょう。
収納計画の基本ステップ
- 現在の荷物量を把握する
まずは、今持っている荷物の量を確認しましょう。衣類・寝具・本・書類・家電・趣味道具・季節用品など、現状を全てリストアップします。現在「収納が足りない」と感じている場合は、1.5倍の収納スペースを目安に確保するのがおすすめです。
- 将来の変化を想定する
家族構成やライフスタイルの変化で、荷物は増えていきます。最低でも5〜10年後を想定して、余裕を持った収納計画を立てましょう。
④建築会社選びを慎重に行う
家づくりの成功は、建築会社選びで8割決まると言っても過言ではありません。価格やデザインだけでなく、信頼できるパートナーを見つけることが重要です。
建築会社選びのチェックポイント
|
観点 |
確認内容 |
|
施工実績と評判 |
年間棟数・創業年数・施工事例・口コミ・受賞歴 |
|
住宅性能へのこだわり |
断熱・気密・耐震等級の公開、性能測定の有無 |
|
価格の透明性 |
坪単価に含まれる内容、標準仕様とオプションの区分 |
|
提案力とヒアリング力 |
要望を丁寧に聞き、複数案を比較検討できるか |
|
アフターサポート |
定期点検の頻度・保証内容・緊急対応の有無 |
|
営業担当者との相性 |
説明の分かりやすさ・誠実さ・対応の速さ |
比較検討の進め方
- 資料請求:各社のカタログを取り寄せて特徴を把握
- 展示場見学:実際の空間で質感や仕様を確認
- 概算見積もり:同条件で複数社を比較
- 完成見学会:実際に建てた家を見てリアルな住み心地を体感
安さだけで選ぶと、後からオプション費用がかさむケースもあります。信頼できる担当者と、納得いくまで話し合いながら進めることが何より大切です。
熊本で注文住宅を建てるなら「アイ-ウッド」

ここまで、家づくりの流れや後悔しないためのポイントをお伝えしてきました。理想の家づくりを実現するには、信頼できるパートナー選びが何より重要です。
アイ-ウッドは地元熊本で創業して半世紀以上。これまで約8,000棟、地域の皆さまが安心して暮らせる住まい、愛着を感じずっと住みたくなる住まいをつくり続けてきました。
「お客様にマイホームをずっと好きでいてほしい。」
「ずっと住みたいと思ってほしい。」
その想いを原点に、一人ひとりの理想の暮らしを丁寧に形にしています。
他社様では断られたような要望であっても、 どうすれば実現できるかを一緒に考え抜くのがアイ-ウッドのスタイルです。
これまでも「体育館のような家に住みたい」「本棚の後に隠し扉を設けたい」など、さまざまなご要望を形にしてきました。
お客様の施工事例
実際にアイ-ウッドで家を建てられたお客様の事例をご紹介します。
①食卓とは別に、仕込み用の本格的な厨房を設けたお家

キッチンカーで活躍するイタリアンシェフのお客様。「家でも本格的な仕込みができる厨房が欲しい」という要望を叶えるため、家族の食卓とは別に、業務用仕様の厨房スペースを設けました。限られた予算の中で、動線や換気性能にも配慮し、暮らしと仕事の両立を実現しています。
注文住宅の施工事例:生き方を投影した「何も制限されない」自由な家づくりを
②隠し扉の奥に趣味の部屋がある、遊び心満載の住まい

「体育館のような広い空間で遊びたい」というご主人の夢を叶えた住まい。本棚の裏には隠し扉と趣味の部屋を設け、遊び心と機能性を両立しました。家族の笑顔があふれる、世界に一つだけの自由設計の家です。
注文住宅の施工事例:隠し扉と秘密の部屋が遊び心をくすぐる大空間の家
③土足で暮らすというセオリー外の家づくり

「家の中でも土足で過ごしたい」という、欧米スタイルのライフスタイルを実現。店舗で使われる土足用のフローリングを採用し、機能性とデザイン性を両立しました。「自分たちらしい暮らし」を大切にするご家族の思いを形にしています。
注文住宅の施工事例:家族ならではの“暮らし方”を大切に守り、育てる家
少しでもアイ-ウッドの家づくりが気になったら、LINEのお友だち登録をしてみませんか。アイ-ウッドのLINE公式アカウントでは、見学会や分譲地情報、住宅探しやライフスタイルのヒントなど、家づくりに役立つ最新情報をいち早くお届けしています。
▼今すぐLINEで「家づくりのヒント」を受け取る▼


